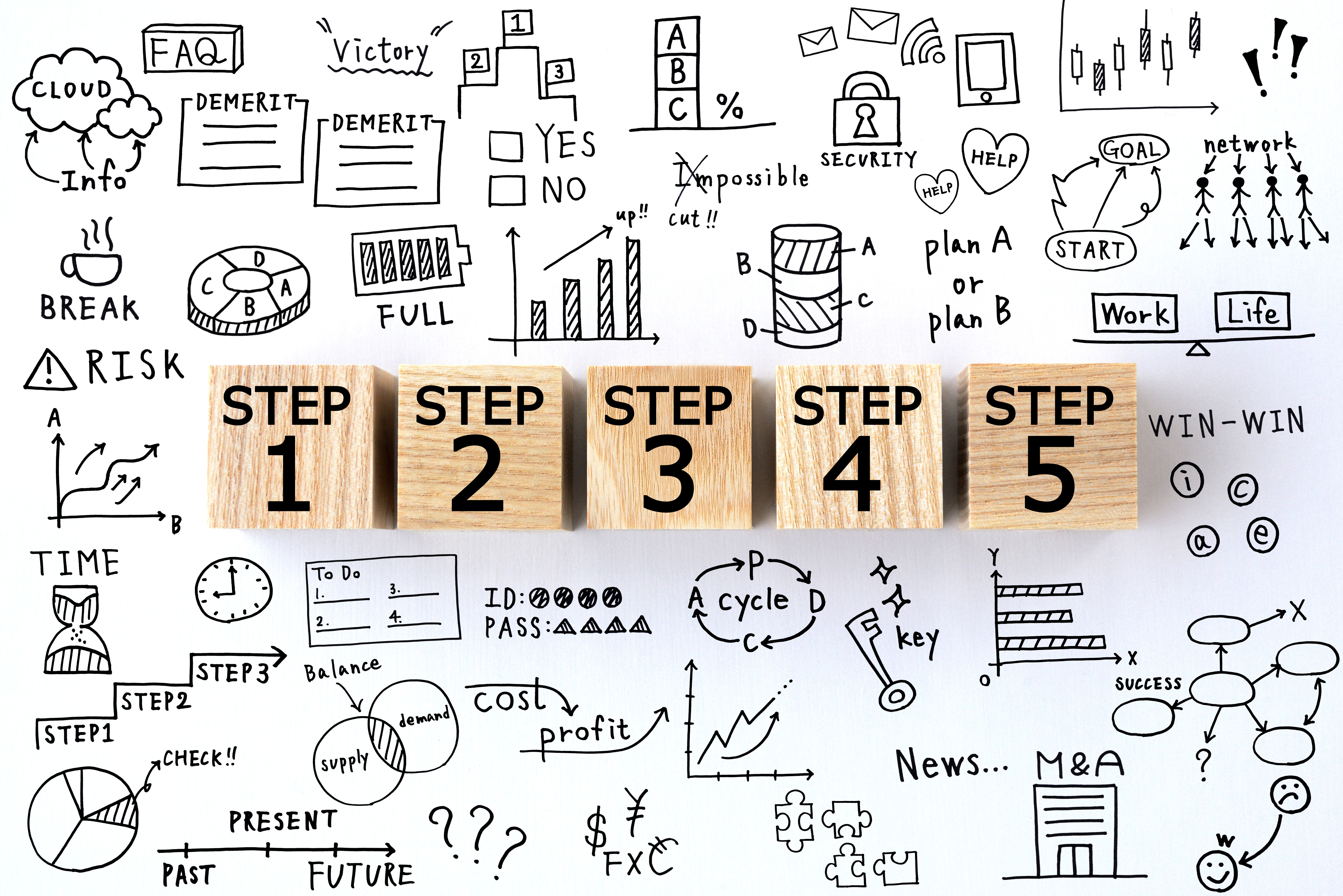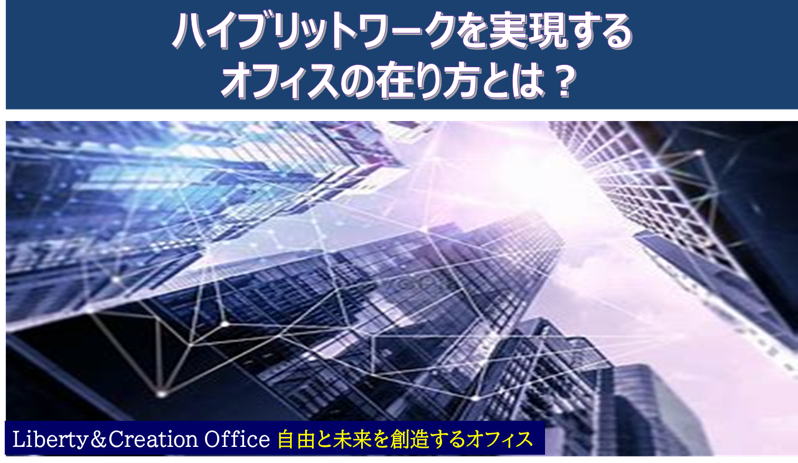サイト内検索
ソリューションコラム
- トップページ
- ソリューションコラム
- すぐ実践できるペーパーレス化の方法を紹介!
メリットや注意点、進まない原因なども解説
すぐ実践できるペーパーレス化の方法を紹介!
メリットや注意点、進まない原因なども解説
2023.01.07
ペーパーレス化とは、電子化によって紙を使うのをやめることです。仕事の効率化やコストカットにつながることや、SDGsとの関連もあって昨今注目されています。
ところが、どうやってペーパーレス化をするかという方法論についてはあまり知られていません。実際、日系企業におけるペーパーレス化は、あまり進んでいないのが現状です。
そこで今回は、すぐに実行できるペーパーレス化の方法を紹介します。ペーパーレス化に関心のある経営者や幹部の方は、ぜひ以下をお読みください。
目次
ペーパーレス化のメリットは?
ペーパーレス化のメリットは、第一に業務を効率化できることです。パソコンやスマホから簡単に資料を入手できるようになるので、文書の検索にかかる時間を減らせます。また紙資料を印刷したり、整理したりといった手間もかかりません。
第二に、コスト削減につながることも、ペーパーレス化の大きなメリットです。用紙代や印刷代、紙資料を整理する社員の残業代などを削減できます。とくに昨今は物価高で用紙代が上がっているので、ペーパーレス化をすれば、月々の固定費がかなり変わってくるはずです。
さらにペーパーレス化には、セキュリティの強化につながるという利点もあります。電子化した資料には、パスワードやアクセス制限などのロックをかけられるので、情報漏えいなどのリスクが下がります。加えて、時間とともに劣化したり、火災で焼失したりする恐れがないことも魅力です。
インク革命.COMのアンケート調査によると、2021年度にペーパーレス化を実施した企業は、27.6%にとどまりました。
日系企業のペーパーレス化が進まない要因としては、ITツールへの不安が挙げられます。ペーパーレス化はすなわち電子化なので、経営者を含めた社内の人間が、ITツールの操作に自信を持てないと、実行しにくいです。
またペーパーレス化のデメリットとして、導入費用が挙げられます。低予算でやる方法もありますが、システムや機器を入れるとなると、それなりの費用が必要です。とはいえ、ITツールの導入には補助金も使えるので、基本的にやる気さえあればペーパーレス化は実現できます。
2022年1月1日に施行された改正・電子帳簿保存法は、企業のペーパーレス化を後押ししています。同改正では、国税関係帳簿の電子化にかかる事前承認制度が廃止されるとともに、電子帳簿の保存に関する要件が緩和されました。
現在は、国税関係帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)のほか、契約書や領収書、貸借対照表、損益計算書といった書類が、以前より簡単に電子化できます。そのため、ペーパーレス化に踏み出すには、今が良い機運だといえます。
第二に、コスト削減につながることも、ペーパーレス化の大きなメリットです。用紙代や印刷代、紙資料を整理する社員の残業代などを削減できます。とくに昨今は物価高で用紙代が上がっているので、ペーパーレス化をすれば、月々の固定費がかなり変わってくるはずです。
さらにペーパーレス化には、セキュリティの強化につながるという利点もあります。電子化した資料には、パスワードやアクセス制限などのロックをかけられるので、情報漏えいなどのリスクが下がります。加えて、時間とともに劣化したり、火災で焼失したりする恐れがないことも魅力です。
現状は3割未満の企業しか実施せず【なぜ進まない?】
インク革命.COMのアンケート調査によると、2021年度にペーパーレス化を実施した企業は、27.6%にとどまりました。
日系企業のペーパーレス化が進まない要因としては、ITツールへの不安が挙げられます。ペーパーレス化はすなわち電子化なので、経営者を含めた社内の人間が、ITツールの操作に自信を持てないと、実行しにくいです。
またペーパーレス化のデメリットとして、導入費用が挙げられます。低予算でやる方法もありますが、システムや機器を入れるとなると、それなりの費用が必要です。とはいえ、ITツールの導入には補助金も使えるので、基本的にやる気さえあればペーパーレス化は実現できます。
電子帳簿保存法の改正が追い風に
2022年1月1日に施行された改正・電子帳簿保存法は、企業のペーパーレス化を後押ししています。同改正では、国税関係帳簿の電子化にかかる事前承認制度が廃止されるとともに、電子帳簿の保存に関する要件が緩和されました。
現在は、国税関係帳簿(仕訳帳や総勘定元帳)のほか、契約書や領収書、貸借対照表、損益計算書といった書類が、以前より簡単に電子化できます。そのため、ペーパーレス化に踏み出すには、今が良い機運だといえます。
ペーパーレス化の方法10選
ペーパーレス化の方法は、「これからの書類を電子化する取り組み」と「過去の書類を電子化する取り組み」に大別できます。以下ではそれぞれの取り組みについて、具体的な方法を紹介するので参考にしてください。
これから作ったり、受け取ったりする資料をペーパーレス化するには、以下の方法がおすすめです。すべてを網羅しなくても良いので、必要なものや試しやすいものを実践してみましょう。
最初は電子ファイルを保存することから始めましょう。普段なら印刷してファイルに入れるところを、PDFデータにしてストレージなどに保存する。これだけでも立派なペーパーレス化です。
なお、文書のPDF化には、Wordのエクスポートや変換ソフトなどを用いると良いでしょう。
請求書や見積書といった帳票も、比較的簡単にペーパーレス化できます。多くの場合、帳票はパソコンで作っているはずなので、作ったものをそのままメールやチャットで取引先に送るだけです。これで帳票を印刷したり、郵送したりする手間が省けます。
電子契約サービスを利用すれば、契約書も簡単に電子化できます。電子契約サービスなら、電子契約に必要なIT環境(電子サインやタイプスタンプなど)がパッケージで利用できるので手軽です。契約書のペーパーレス化が実現すれば、テレワークでも契約業務を円滑に行えるようになります。
大規模なペーパーレス化を望むなら、バックオフィスに基幹業務システム(会計システムや人事管理システムなど)を入れて、デジタル化するのもおすすめです。
管理部門には、伝票や領収書、給与明細、備品管理表をはじめ、たくさんの資料があります。そのため、管理部門をペーパーレス化すれば、大幅な効率化・コストカットにつながります。
現場では、紙資料をなくす代わりに、タブレットやモニターを導入すると便利です。膨大な資料を一つの画面で見られるため、業務上の利便性が高まることはもちろん、スペースの効率化にもつながります。例えば、製造業では、図面や資料を挟んだクリップボードをタブレットに持ち替え、成功している企業が複数あります。
A. これからの書類をペーパーレス化する方法
これから作ったり、受け取ったりする資料をペーパーレス化するには、以下の方法がおすすめです。すべてを網羅しなくても良いので、必要なものや試しやすいものを実践してみましょう。
1. まずは電子ファイルを保存することから始める
最初は電子ファイルを保存することから始めましょう。普段なら印刷してファイルに入れるところを、PDFデータにしてストレージなどに保存する。これだけでも立派なペーパーレス化です。
なお、文書のPDF化には、Wordのエクスポートや変換ソフトなどを用いると良いでしょう。
2. 請求書などの帳票をメールで送るようにする
請求書や見積書といった帳票も、比較的簡単にペーパーレス化できます。多くの場合、帳票はパソコンで作っているはずなので、作ったものをそのままメールやチャットで取引先に送るだけです。これで帳票を印刷したり、郵送したりする手間が省けます。
3. 電子契約サービスで契約書もペーパーレス化
電子契約サービスを利用すれば、契約書も簡単に電子化できます。電子契約サービスなら、電子契約に必要なIT環境(電子サインやタイプスタンプなど)がパッケージで利用できるので手軽です。契約書のペーパーレス化が実現すれば、テレワークでも契約業務を円滑に行えるようになります。
4. バックオフィスには基幹業務システムを導入する
大規模なペーパーレス化を望むなら、バックオフィスに基幹業務システム(会計システムや人事管理システムなど)を入れて、デジタル化するのもおすすめです。
管理部門には、伝票や領収書、給与明細、備品管理表をはじめ、たくさんの資料があります。そのため、管理部門をペーパーレス化すれば、大幅な効率化・コストカットにつながります。
5. 現場にタブレットやモニターを入れる
現場では、紙資料をなくす代わりに、タブレットやモニターを導入すると便利です。膨大な資料を一つの画面で見られるため、業務上の利便性が高まることはもちろん、スペースの効率化にもつながります。例えば、製造業では、図面や資料を挟んだクリップボードをタブレットに持ち替え、成功している企業が複数あります。
6. FAXは印刷せずにPDFデータで出力
FAXをよく利用する場合は、ペーパーレスFAXを導入するのがおすすめです。ペーパーレスFAXとは、FAXをデータで管理できるサービスのこと。送られてきたFAX文書を、印刷せずにPDFデータとして保存できます。メールのような感覚でFAXを扱えるようになって便利です。
7. ビジネスチャットやオンラインストレージを始める
ペーパーレス化した資料の送信・共有には、ビジネスチャットやオンラインストレージを活用しましょう。社員がデータにアクセスしやすい環境を作ることで、ペーパーレス化の効果がより高まります。反対に、データを利活用する環境を整備しないと、紙資料がなくなったことで、かえって社員が不便を感じる恐れもあります。
8. 承認作業はワークフローシステムで効率化
経費精算書や稟議書といった申請書の承認作業は、ワークフローシステムを入れることでペーパーレス化が可能です。デジタルな申請フォームを通じて、スムーズに申請・承認・却下の作業が行えます。
申請書を作って印刷し、上司や各部の担当者を回ってハンコをもらうといった作業をなくせるので、大変おすすめです。またシステムでは、金額計算や内容確認が自動でなされるため、申請書の入力ミスも減らせます。
B. 過去の書類をペーパーレス化する方法
すでに発行されている紙資料を電子データに変換し、ペーパーレス化するには、以下2つの方法を実践するのがおすすめです。
9. 手書きや活字はOCRでデータ化する
手書きや活字の文書は、OCRを活用することでペーパーレス化できます。OCRとは、文字をスキャナやカメラで読み取って電子化する方法のことです。日本語では「光学的文字認識」といいます。
最近はスマホやタブレットのカメラを利用するOCRアプリも多数登場しており、手軽に既存文書のデータ化が可能です。
10. スキャニングサービスを利用する
紙資料が膨大にある場合は、外部のスキャニングサービスを利用するのも良いでしょう。スキャニングサービスでは、書庫や倉庫などに保管されている資料を、専門業者にまとめてデータ化してもらえます。社内にスキャナーを持ち込んで作業をしてもらえるサービスもあり、気軽に紙資料を電子化したい場合におすすめです。
ペーパーレス化を進める流れ【5つのステップ】
実際にペーパーレス化を進める際は、以下の流れにしたがって準備・実行するのが良いでしょう。やろうと思えば、今日・明日にでも始められることなので、ぜひすぐにチャレンジしてみてください。
ペーパーレス化の目的を明確にするために、まずは紙資料に関わる現状の問題点を洗い出しましょう。例えば「紙ベースの集計作業に時間がかかってミスも多い」、「ファイルをしまえる棚がもうない」など。必要に応じて、現場の社員にヒアリングを行うのも良いでしょう。
業務上の課題を洗い出したら、それをもとにペーパーレス化の目的を決めます。大体は業務の効率化かコストカットのどちらかになるでしょう。そのほか、テレワークの推進やセキュリティ対策といったことも、ペーパーレス化の目的になり得ます。
あわせてペーパーレス化の範囲も決めてください。一気にすべて電子化できれば理想的かもしれませんが、予算や労力を考えると難しいので、優先順位を決めて実行するのがおすすめです。例えば、生産性を向上させるには、やはり現場を電子化・効率化するのが良いでしょう。コストカットであれば、バックオフィスにシステムを入れるだけでも、かなり効果が出るはずです。
続いて、それぞれのペーパーレス化に最適なITツールを選定し、導入します。ITツールの例は、タブレットやモニター、業務システム、OCRソフト、ビジネスチャットなどさまざまです。なお、導入するツールの種類や性質によっては、「IT導入補助金」などが使える可能性もあるので、必要に応じてチェックしてみてください。
ITツールの導入と並行して、ペーパーレス化に関する社内でのルールを決めておくことが大切です。ルールを整備しないまま電子化してしまうと、社員の間で混乱が生じる恐れがあります。具体的には、ファイルへの名前の付け方や保存方法、各機器の用途などを決めておくのが良いでしょう。
ペーパーレス化の実行後は、定期的に検証を行い、当初の目的が達成されているかを確かめましょう。効果が出ていないようなら、ペーパーレス化の方法やツールの活用方法などを改善するのが望ましいです。検証の方法としては、社員に感想を聞いたり、データを確認したりといった事柄が挙げられます。
1. 紙資料に関わる現状の問題点を洗い出す
ペーパーレス化の目的を明確にするために、まずは紙資料に関わる現状の問題点を洗い出しましょう。例えば「紙ベースの集計作業に時間がかかってミスも多い」、「ファイルをしまえる棚がもうない」など。必要に応じて、現場の社員にヒアリングを行うのも良いでしょう。
2. ペーパーレス化の目的と範囲を決める
業務上の課題を洗い出したら、それをもとにペーパーレス化の目的を決めます。大体は業務の効率化かコストカットのどちらかになるでしょう。そのほか、テレワークの推進やセキュリティ対策といったことも、ペーパーレス化の目的になり得ます。
あわせてペーパーレス化の範囲も決めてください。一気にすべて電子化できれば理想的かもしれませんが、予算や労力を考えると難しいので、優先順位を決めて実行するのがおすすめです。例えば、生産性を向上させるには、やはり現場を電子化・効率化するのが良いでしょう。コストカットであれば、バックオフィスにシステムを入れるだけでも、かなり効果が出るはずです。
3. ITツールを選んで導入する
続いて、それぞれのペーパーレス化に最適なITツールを選定し、導入します。ITツールの例は、タブレットやモニター、業務システム、OCRソフト、ビジネスチャットなどさまざまです。なお、導入するツールの種類や性質によっては、「IT導入補助金」などが使える可能性もあるので、必要に応じてチェックしてみてください。
4. ペーパーレス化のルールを決める
ITツールの導入と並行して、ペーパーレス化に関する社内でのルールを決めておくことが大切です。ルールを整備しないまま電子化してしまうと、社員の間で混乱が生じる恐れがあります。具体的には、ファイルへの名前の付け方や保存方法、各機器の用途などを決めておくのが良いでしょう。
5. ペーパーレス化の効果を検証し、適宜改良する
ペーパーレス化の実行後は、定期的に検証を行い、当初の目的が達成されているかを確かめましょう。効果が出ていないようなら、ペーパーレス化の方法やツールの活用方法などを改善するのが望ましいです。検証の方法としては、社員に感想を聞いたり、データを確認したりといった事柄が挙げられます。
ペーパーレス化のポイントと注意点
ペーパーレス化をうまく実現するには、以下の内容を意識するのがおすすめです。
ペーパーレス化をやると決断したなら、経営者がそれを牽引すべきです。例えば、社内の文書をすべて電子化する場合、経営者は紙資料を一切使わないようにしましょう。「どうせ社長は紙で見るから」と社員に思われてしまったら、ペーパーレス化に十分な効果が期待できなくなります。
特定商取引法における重要事項説明書やクーリングオフ書面など、現行法では一部電子化できない書類も存在します。「相手の承諾があれば電子化できる」といった細かい決まりもあるため、ペーパーレス化の前に法務担当や外部の専門家に確認するのもおすすめです。
とはいえ、書面化の義務は緩和される方向で法改正が進んでいるので、ペーパーレス化できないものはそう多くありません。
請求書のペーパーレス化や電子契約の導入など、取引先との関連が大きいものについては、相手の意向を確認すべきです。取引先に相談せず、勝手にペーパーレス化してしまうと、トラブルに発展する恐れもあるので気をつけましょう。
経営者が率先してペーパーレス化を実行する
ペーパーレス化をやると決断したなら、経営者がそれを牽引すべきです。例えば、社内の文書をすべて電子化する場合、経営者は紙資料を一切使わないようにしましょう。「どうせ社長は紙で見るから」と社員に思われてしまったら、ペーパーレス化に十分な効果が期待できなくなります。
一部ペーパーレス化できない書類もあるので注意
特定商取引法における重要事項説明書やクーリングオフ書面など、現行法では一部電子化できない書類も存在します。「相手の承諾があれば電子化できる」といった細かい決まりもあるため、ペーパーレス化の前に法務担当や外部の専門家に確認するのもおすすめです。
とはいえ、書面化の義務は緩和される方向で法改正が進んでいるので、ペーパーレス化できないものはそう多くありません。
取引先の意向を聞くことも大切
請求書のペーパーレス化や電子契約の導入など、取引先との関連が大きいものについては、相手の意向を確認すべきです。取引先に相談せず、勝手にペーパーレス化してしまうと、トラブルに発展する恐れもあるので気をつけましょう。
まとめ
ペーパーレス化の方法は、第一歩として文書を印刷せず電子ファイルで保存すること。その後は、目的に応じてシステムや端末、アプリなどを導入しましょう。
企業の大半がまだペーパーレス化を実現していない今、率先して紙文書をやめることは、生産性を高めて競合優位性を確保するチャンスです。これを機会にぜひ、今回紹介した方法を実践し、いち早くペーパーレス化を実現しましょう。
企業の大半がまだペーパーレス化を実現していない今、率先して紙文書をやめることは、生産性を高めて競合優位性を確保するチャンスです。これを機会にぜひ、今回紹介した方法を実践し、いち早くペーパーレス化を実現しましょう。
- 関連ページ:
- ペーパーレス推進支援サービス